CloudNative Days Summer 2025 オンライン参加メモ
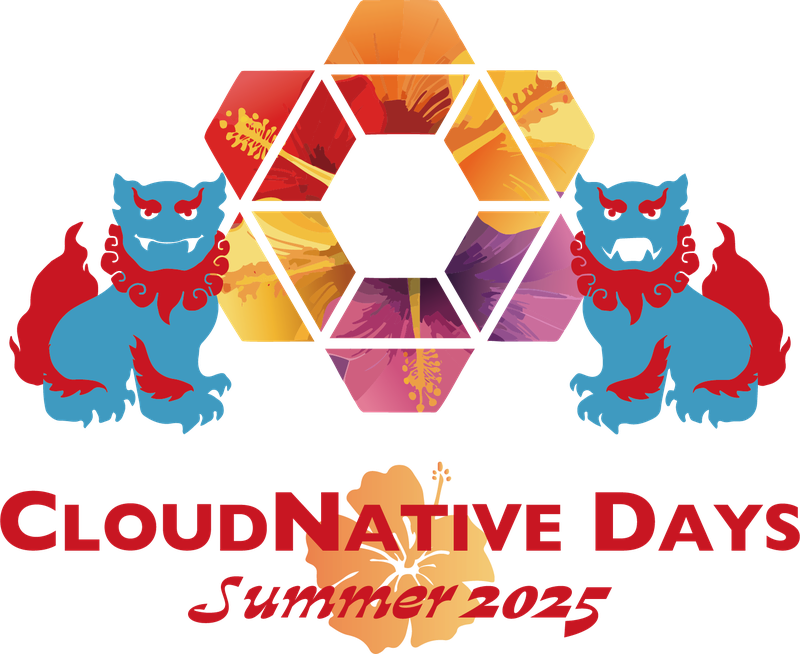
1. はじめに
先日開催されたCloudNative Days Summer 2025にオンライン参加しました。現地には行けなかったので会場の熱気を肌で感じることはできませんでしたがでしたが、多くのセッションから学びを得られました。本ブログでは、私がデータ基盤案件に従事し興味があったデータエンジニアリング関連で視聴した感想・メモを書きたいと思います。
2.クラウドデータ基盤で切り拓く沖縄DXの可能性
沖縄が直面する課題を分析し、それに対するDXという解決策を、データ活用という視点から詳細に解説していました。特に、沖縄独自の地域特性を踏まえつつ、データ基盤導入による具体的な効果や導入のアプローチまで言及されていて非常に興味深いセッションでした。個人的に沖縄はIT企業が多くDXが進んでいると思っていましたが課題もあるのだと。地域特性もDX推進に影響を与えることは他の地方都市もどのような感じなのか気になるところです。
- 沖縄が抱える地域課題
- 観光客数が年間1000万人に達する一方で、人口減少と高齢化が進む
- 有人離島への行政サービス、医療、教育の提供課題
- 沖縄特有のDX課題
- DX認知度が低く、取り組みが遅れている
- DX人材不足
- 企業が那覇に集中
- 離島や北部ではIT人材との接点がない
- 若いIT技術者が県外に出てしまう
- 中小企業が中心の産業構造
- 観光業への依存度が高い
- 地域特性
- ゆいまーる精神(助け合いの精神)
- 変化への対応や新しい成長を逃してしまう
- ゆいまーる精神(助け合いの精神)
- 沖縄県はDX推進計画を策定し、生活、産業、行政の各分野でデジタル化を進めている
- しかし現場レベルではDXの対する理解不足や体制構築のなどの課題がある
- データ活用が課題解決するキーとなるとし、ビジネス成長を促進する攻めのDXと業務効率化のための守りのDXの両面を推進する必要性がある
- 小売業におけるデータ基盤導入の事例
- 各部署のデータをExcelで手動で加工・集計してレポートを作成している運用が多い
- 課題
- データの一元管理ができていない
- Excelでのデータ加工・レポート作成にコストがかかる
- 分析用のダッシュボードがなく意思決定が難しい
- 課題
- データ基盤の導入
- 部署ごとのデータソースをS3に集約し、DataLake、DWHなどを活用して分析用途に応じたデータマートを構築する
- データ加工処理を自動化し、BIツールを用いて現場担当者や経営層が参照できるようにする
- データの一元管理と手動データ加工処理の自動化
- 成果
- 経営判断のためのダッシュボードによる意思決定のスピード向上
- データ基盤による事業ニーズへの順応
- マーケティングや需要予測への活用
- 現場担当者の運用コスト削減
- 各部署のデータをExcelで手動で加工・集計してレポートを作成している運用が多い
- データ基盤導入のポイント
- 小さく始めて大きく育てることで、初期投資を抑えた段階的な導入、事業規模に合わせた拡張が可能
- マネージドサービスやAI/MLサービスを活用して業務自動化を行い人材不足に対応する
- 県外ベンダーとの連携
3.Data EngineeringとCloud Nativeの今と未来
データエンジニアリングとはなんぞや?と言うところや、DBやDWHの歴史からモダンデータスタックとは?と自分では全然言語化できないことを本セッションでわかりやすく解説いただき非常に分かりやすかったです。特に、クラウドがデータエンジニアリングと共に進化してきたこと、AI時代のデータエンジニアリングがAIエージェントへのデータ提供へと役割を拡大していくという今後の展望を感じさせ、非常に興味深かかったです。「コスト破産して1億円吹っ飛ばしましょう」は面白かったです(笑)
- データエンジニアリングとは
- 機械学習やデータ分析のためのプラットフォーム
- 全てのデータ業務を一人で行うのは不可能であり、チームで協力する必要がある
- エンタープライズ環境におけるデータ基盤の役割として、様々なシステムからデータを集約し、分析可能な状態にする
- DBの歴史とDWHの登場
- DBは1970年代のRDBから始まり、データ基盤、ビッグデータ、そしてクラウドへと進化してきた
- 2012年にDWHが登場し、その後、様々なDWHが登場
- Redshift、Snowflake、BigQuery、Synapseなど
- DWHとは分析用のDBのことである
- 様々な製品やOSSが生まれ、データ系のエコシステムが広がっていった
- クラウドがデータエンジニアリングに適している
- データが現実世界から発生するため、規模やキャパシティの予測が難しいことが、クラウドが適している
- ソフトウェアエンジニアリングがトップダウンであるのに対し、データエンジニアリングはボトムアップでデータを見て設計していく
- 用途が予測しづらいデータや、データ処理に柔軟にリソースを追加したい場合に、クラウドが適している
- クラウドなしでは現在のデータエンジニアリングは考えられない
- モダンデータスタック
- クラウドネイティブな技術や製品、OSSを組み合わせてデータ基盤を構築する。要するにクラウドを使い倒す
- 課題
- コスト管理の重要性を挙げている。
- クラウド破産しないために、FinOpsという概念を使う。
- データインフラへの投資対効果や、収益性の最大化など課題である
- コスト管理の重要性を挙げている。
- データエンジニアの仕事
- 顧客のデータ分析ニーズに応じた製品導入
- データパイプラインの構築
- セマンティックレイヤーの整備
- データモデリング
- 組織ごとのデータエコシステムの成熟度に応じて、データ基盤を段階的に構築していくことが重要
- AI時代のデータエンジニアリング
- AIの進化により、データ利用者が人間だけでなくAIエージェントにも広がっていく
4. Road to KubeCon Japan 2025
日本でのCloud Native技術の普及が海外に比べて遅れており、資格試験の受験者数も少ないというのは驚きでした。CNCJの積極的な活動により受験者数が増加し、活動1年でKubeConの日本開催まで決定したことは素晴らしいと思いました。私も参加するので非常に楽しみにしています。
- 日本国内のCloud Nativeの現状
- Cloud Native関連の資格試験(CKA,CKSなど)日本における受験者数が非常に少ないことが課題
- インドの1/8、中国の1/5、韓国の1/2
- Cloud Native技術を使っている企業やエンジニアが少ない。
- Cloud Native技術の普及率が欧米と比較して低いだけでなく、コンテナやマイクロサービスといった基本的な技術の認知度も低い
- Cloud Native関連の資格試験(CKA,CKSなど)日本における受験者数が非常に少ないことが課題
- CNCJの発足・活動
- 2024年がCNCJ元年
- 活動の結果、関連資格の日本の受験者数が韓国に追いつき、中国との差も縮まった
- KubeConを日本に招致したい
- KubeCon Japanが日本で開催されることの意義として、海外の開発者との交流、世界への情報発信がある
- CNCJメンバーのロビー活動により、わずか1年でKubeCon Japanの日本開催が決定した
5.終わりに
今回はデータエンジニアリング関連のセッションを中心に書きましたが、それ以外のセッションも大変興味深く多くの学びがありました。まだ視聴できていないアーカイブ動画も残っているのでこれから追っかけ視聴したいと思います。オンライン参加でも十分な学びがありましたが、次は熱量を肌で感じたいので現地参加できたらと思います。





