AIを最大限に活用するために。Googleのプロンプトエンジニアリングをざっくり解説
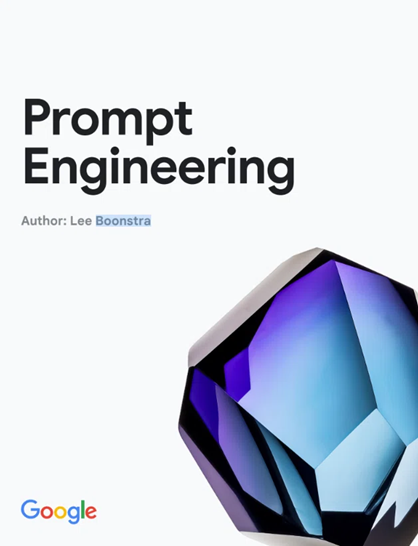
はじめに
生成AIが私たちの仕事や日常に急速に浸透する中、「AIから期待通りの答えが返ってこない」「もっと上手く使いこなしたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。その悩みを解決する鍵こそが「プロンプトエンジニアリング」です。
プロンプトエンジニアリングは、一部の専門家だけのものではありません。いくつかの原則とテクニックを学ぶだけで、誰でもAIの性能を劇的に引き出し、頼れるパートナーへと変えることができます。
今回は、Googleが公開している資料に基づき、プロンプトエンジニアリングの内容を3つのテーマに分けて深く、そして分かりやすく解説していきます。各テーマの最後には内容をまとめた表も用意しましたので、ぜひご活用ください。
なお、このブログはGoogleが2025年2月に公開したプロンプトエンジニアリングに関するホワイトペーパーをもとに作成しています。
1:AIとの対話の質を変える基本テクニック
まず、AIとのコミュニケーションの土台となる基本的なプロンプティング技術を理解しましょう。これらのテクニックを使い分けるだけで、出力の精度は大きく変わります。
1. ゼロショット・プロンプティング:最も手軽な第一歩
これは、AIに事前の例(ショット)を一切与えず、直接タスクを指示する最もシンプルな方法です。「この文章を要約して」「以下のテーマで詩を書いて」といった指示がこれにあたります。
- 強み: 手軽でスピーディー。簡単なタスクであれば十分機能します。
- 弱み: AIがタスクの意図や期待するアウトプットの形式を誤解する可能性があります。特に、回答のスタイルや構造に特定のフォーマットを求める場合に限界があります。
2. ワンショット&フューショット・プロンプティング:手本を見せて導く
AIの精度を向上させる非常に効果的な方法が、1つ(ワンショット)または複数(フューショット)の「手本(例)」を示すことです。これにより、AIはあなたが何を求めているのか、どのような形式で答えてほしいのかを具体的に学習します。
- 強み: 期待する出力のパターン、スタイル、構造をAIに明確に伝えられます。ゼロショットに比べて、格段に回答の質が安定し、精度が向上します。
- フューショットの目安: 一般的に、3〜5個の例を示すことが推奨されていますが、タスクの複雑さに応じて調整が必要です。
3. 役割(ペルソナ)を与える:専門家になりきらせる
AIに特定の役割を与えることで、出力のトーン、スタイル、専門性をコントロールできます。「あなたは〇〇です」と定義するだけで、AIはその役割にふさわしい応答を生成しようとします。
- 効果: 回答に一貫性が生まれ、特定の文脈に沿った、より質の高いコンテンツを作成できます。
【まとめ】基本プロンプティングテクニック
| テクニック名 | 概要 | どんな時に使う? | プロンプト例 |
| ゼロショット | 例を見せずに直接指示する | 簡単で明確なタスクを素早く処理したい時 | 「このEメールを日本語に翻訳して。」 |
| ワンショット/フューショット | 1つまたは複数の手本(例)を示す | 回答の形式やスタイルを指定したい時、精度を高めたい時 | 「例:犬→dog, 猫→cat。車→?」 |
| 役割(ペルソナ)付与 | AIに特定の役割やキャラクターを演じさせる | 特定の視点やトーンで文章を生成したい時 | 「あなたはプロの編集者です。この記事を校正してください。」 |
2:AIの思考力を覚醒させる高度なテクニック
基本的なテクニックをマスターしたら、次はAIの思考プロセスそのものに介入し、より複雑で論理的な問題を解決させるための高度なテクニックに挑戦しましょう。
1. 思考の連鎖(Chain of Thought - CoT):答えだけでなくプロセスを問う
CoTは、特に算数や論理パズルなど、中間的なステップが必要な問題で絶大な効果を発揮します。単に答えを求めるのではなく、**「ステップバイステップで考えて」や「順を追って説明して」**のように、AIに思考の過程を記述させるテクニックです。
- なぜ効果的なのか?: 人間が難しい問題を解くときにメモを取るように、AIも思考のステップを一つずつ生成することで、複雑な問題に対する集中力を維持し、より正確な結論にたどり着くことができます。
例:年齢を当てる問題
私が3歳のとき、パートナーは私の3倍の年齢でした。今、私は20歳です。パートナーは何歳ですか? ステップバイステップで考えてください。
2. ステップバック・プロンプティング:一歩引いて本質を考えさせる
これは、具体的な質問に直接答える前に、一歩引いた視点から、より一般的で抽象的な概念や原則について考えさせるテクニックです。背景知識を活性化させることで、最終的な回答の質と洞察力を高めます。
例:ゲームのストーリーライン作成
ステップ1(抽象化): 人気の一人称シューティングゲームにおいて、挑戦的で魅力的な設定を5つ挙げてください。ステップ2(具体化): (ステップ1の回答を受けて) これらのテーマのうち1つを選び、具体的なストーリーラインを書いてください。
3. ReAct (Reason and Act):思考と行動をループさせる
ReActは、「思考(Reason)」と「行動(Act)」を組み合わせた、よりエージェント的なアプローチです。AIはタスクを解決するために計画を立て、検索などの外部ツールを使って情報を収集(行動)し、その結果を基に次の思考を組み立てます。
- 活用シーン: 最新情報が必要な質問、複数の情報を統合する必要があるタスクなどで非常に強力です。
【まとめ】応用プロンプティングテクニック
| テクニック名 | 概要 | どんな時に使う? | プロンプト例のキーワード |
| 思考の連鎖 (CoT) | AIに思考プロセスを段階的に説明させる | 計算問題、論理パズル、複雑な推論が必要な時 | 「ステップバイステップで考えて」 |
| ステップバック | 具体的な問いの前に、抽象的・一般的な問いを挟む | 創造性や深い洞察が求められるタスクの時 | 「まず、**〜の原則について説明して。**その上で…」 |
| ReAct | AIが外部ツール(検索など)を使い、情報収集と推論を繰り返す | 最新情報や外部の知識が必要な時 | (主にAPI経由で利用)「(ツール利用を許可した上で)今日の東京の天気は?」 |
3:今日から使えるプロンプト作成のベストプラクティス
最後に、日々の業務や創作活動で高品質なアウトプットを得るための、普遍的なベストプラクティスを紹介します。これらの習慣を身につけることが、プロンプトエンジニアへの近道です。
- 明確かつ具体的に指示する(Clarity & Specificity)
曖昧なプロンプトは曖昧な答えしか生みません。誰が読んでも同じように解釈できるレベルまで、具体性を高めましょう。 - 制約よりも肯定的な指示を(Instructions over Constraints)
「〜しないでください」という否定的な制約は、AIを混乱させることがあります。代わりに、「〜してください」という肯定的な指示で導きましょう。 - 複雑なタスクは分割して依頼する
一度に複数のことを要求するのではなく、タスクをより小さなサブタスクに分割し、対話形式で進めることで、各ステップの質を高めることができます。 - アウトプット形式を指定する
ブログ記事、メール、箇条書き、表、JSON、Markdownなど、希望する出力形式を明確に指定することで、後工程の作業を大幅に削減できます。 - 試行錯誤を記録し、文書化する
完璧なプロンプトは、反復的なテストと改善の末に生まれます。どのプロンプトが良い結果を生んだのかを記録しておくことは、あなただけの貴重な資産となります。
【まとめ】プロンプト作成のベストプラクティス
| ベストプラクティス | DO(推奨されること) | DON'T(避けるべきこと) |
| 明確性と具体性 | タスク、文脈、対象者、文字数などを詳細に指定する | 「いい感じに」「適当に」といった曖昧な表現 |
| 指示の方法 | 「〜してください」という肯定的で直接的な指示 | 「〜しないで」という否定的な制約の多用 |
| タスクの複雑さ | 複雑なタスクは、より単純な複数のステップに分解する | 1つのプロンプトに多くの要求を詰め込む |
| 出力形式 | Markdown、JSON、表形式など、希望の形式を明確に指定する | 形式を指定せず、AIの解釈に任せる |
| 改善プロセス | 試したプロンプトと結果を記録し、改善を繰り返す | 行き当たりばったりで試し、結果を記録しない |
さいごに
今回ご紹介したテクニックを、より体系的に、そして実践的に学ぶことができる方法が実はあります。
Googleは、公式の学習プログラムとして Google Prompting Essentials を提供しています。この講座では、プロンプトの基本原則から、この記事で触れたような高度なテクニックまでを、ビデオや演習を通じて非常に分かりやすく学ぶことができます。
この記事を書いている私自身も、この講座を受講しました。そして無事すべてのカリキュラムを終え、認定証を受け取ることができました。知識が整理され、AIへの指示の質が格段に上がったと実感しています。
もし、あなたがこの記事を読んで少しでもプロンプトエンジニアリングに興味を持ち、「スキルとして身につけたい」と感じたのであれば、この講座の受講を心からお勧めします。
この一歩が、あなたのAIとの対話を、もっと楽しく、もっと生産的なものに変えてくれるはずです。






