こっちのガイド!?カンバンの実践リファレンス:オープン版カンバンガイド(Open Guide to Kanban)登場!
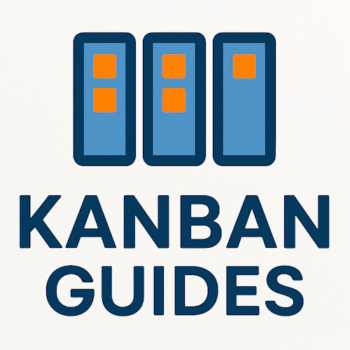
Scrum Guide Expansion Packが提供されたスクラム界隈も盛り上がっていますが、カンバンに関するガイドを提供しているKanban Guidesでも大きな動きがありました。今日はこのカンバン界隈の動きを紹介したいと思います。
なお、本ブログを執筆している2025/07/08時点でも、Kanban Guidesのページも日ごとにどんどん進化していっており、時期が経つにつれてここで紹介した内容と異なる可能性もあります。また、現時点では基本的に英語のみ提供されており、ここで私が翻訳したものは正式な翻訳ではありません。気になる方は、公式サイトKanban Guidesを直接確認してください。
(2025/08/07追記:「Open Guide to Kanban」の日本語名が「オープン版カンバンガイド」となったので、それに合わせてタイトルや見出しなどに追記しました)
カンバンに関する2つのガイド
| ガイド | 目的 | 想定読者 |
|---|---|---|
| The Kanban Guide(カンバンガイド) | 最小限の公式リファレンス | カンバンを初めて利用する人、シンプルで分かりやすいリファレンスを探している人 |
| Open Guide to Kanban(オープン版カンバンガイド) | コミュニティ拡張ハンドブック | 複数のアプローチで作業している人、より詳細なコンテキストと柔軟性が必要な人 |
The Kanban Guide(カンバンガイド)
概要
以前から、正式日本語名「カンバンガイド」として提供されていたガイドです。以前は2020年バージョンだったのですが、2025年5月に最新バージョンが公開されていました。
2025年バージョンの変更点
内容自体にそこまで大きな変更点はないようですが、細かな補足が追加されたり構成などが修正されてたりしていて、読みやすくなっていました。
ガイドを読む上ではそこまで大きなものとはならないでしょうが、「このガイドにおけるカンバンまたはカンバンシステムは、特にknowledge work(知識労働)に関係する」と追記されています。これは、カンバンの背景や意図を掴む上で重要なものだなと感じました。
Open Guide to Kanban(オープン版カンバンガイド)
概要
2025年7月に、カンバンの活用に関する実践的なリファレンスを提供する目的として、The Kanban Guide(カンバンガイド)を基盤として、Open Guide to Kanbanが新たに公開されています。カンバンガイドだけだと、定義は分かりやすいけど、実践に適用するイメージがつきづらいところもある。そこを補うドキュメントと言えます。
ちょうど冒頭で紹介した、スクラムにおけるスクラムガイドとScrum Guide Expansion Packのように、カンバンにおけるカンバンガイドとOpen Guide to Kanbanの関係と考えてよさそうです。その意味では、スクラムよりカンバンの方が知名度や事例が少ないので、相対的にOpen Guide to Kanbanの有用性は高くなるでしょう。
以下、Open Guide to Kanbanを一通り読んでみた感想です。
「知識労働の文脈」の強調
このガイドのサブタイトルに、"In the Context of Knowledge Work"が付いています。上述した2025年バージョンのカンバンガイドにも追加されていましたが、ここはガイドを策定した人たちが焦点を当てたところなのかな、と感じました。具体的には、「トヨタ(製造業の比較的安定したシステム)のカンバン」から「知識労働(複雑性・不確実性が高いシステム)のカンバン」に適用する際に、そのシステムに応じたアプローチを言語化して広めたかったのかなと推測しました。1
他には、WIP制限を使用する目的で、知識労働とトヨタの製造業との比較が記されていました。
- 知識労働:需要がチームのキャパシティを超えないよう、作業項目のフローを調整して過負荷を防ぐ
- 製造業:需要が供給を上回ることを防ぎ、実際の顧客需要と生産を同期させ、在庫を最小限に抑える
ソフトウェア開発以外での適用範囲を例示
実践的なリファレンスという意味では、一例として以下のようなサンプルが例示されていました。カンバンはソフトウェア開発以外でも十分に適用できると思いますが、その旨がガイドに例示されているとイメージしやすいですよね。
ソフトウェアチームでは、カンバンはアイデアからデプロイまでの機能開発を視覚化します。マーケティングチームでは、キャンペーンの設計からローンチまでの追跡に活用できます。
バックログは必須ではない
進行中でない作業項目のリポジトリ(しばしばバックログと呼ばれる)を持つ必要はありません。バックログは創発的であり、作業準備の様々な段階や側面を含む場合があります。バックログを作成すると場合も、それがリスト形式である必要はなく、順序付けされている必要もありません。
スクラム脳からすると、バックログはあってしかるべきだよねって思っていましたが、カンバンのように柔軟性を突き詰めたら必ずしも事前に必要ではないかも、という気付きがありました。とはいえ、現実的にはバックログはあった方が考えやすいことも多そうです。
「必須ではないので、ケースバイケースで用意することができる」ぐらいに捉えておきます。
カンバンに関連する概念やプラクティス
カンバンガイドでは触れられていないけど、実際にカンバンの運用する際に出てくる概念も取り上げられています。例えば以下の概念が紹介されていましたが、今まで何となくの理解しかなかったので、ガイドで説明されているのは参考になりました。
- 適正化(Rightsizing)
適正化とは、作業項目がサービスレベル期待に適合しているかどうか、またはサービスレベル期待に対して大きすぎるため、より小さくても潜在的に価値のある作業項目に分割する必要があるかどうかを評価することを指します。
知識労働における適正化は、作業項目は(カンバンシステムのメンバーの判断により)最大サイズ以下である必要があるものの、必ずしも同じサイズである必要はないという前提に基づいています。
- 現地現物
リーダーシップを発揮する人、つまりリーダーは、実際に見て、耳を傾け、真に理解し、意思決定に必要な事実を収集することです。これは「現地現物」と呼ばれます。
アウトカム・インパクト・価値について言及
アクティビティやアウトプットだけではなく、アウトカム:顧客やユーザーが体験する成果や、インパクト:組織が享受する結果に目を向けることの重要性がより高まってきています。
アウトカムやインパクトの対象ごとに、いくつか例があげられていました。
| 対象 | 説明 |
|---|---|
| 顧客アウトカム | 故障要求の低減、顧客の長期的なコスト削減、顧客のジョブの解決 |
| ユーザーアウトカム | 作業項目を最低コストでより効果的に「完了」することや、使いやすさを向上させること |
| プロダクトステークホルダーのアウトカム | プロダクトの顧客の採用・継続・コンバージョンの傾向、意思決定者とユーザーの指標、プロダクトの市場投入までの時間の傾向 |
| ビジネスステークホルダーのインパクト | コンプライアンス、ビジネスの長期的なコスト削減、ビジネス成果、市場シェアの傾向、全プロダクトにわたる顧客満足度 |
| カンバンシステムメンバーのアウトカム | 様々な能力の向上:心理的フロー、ツール、スキル、技術的負債、技術ドメイン能力、市場ドメイン能力、ビジネスドメイン能力など |
上記のアウトカムと関連して、失敗需要:正しく対応できなかったりすることで発生する需要や、価値実現までの時間なども紹介されています。EBMの重要価値領域に照らし合わせると、A2I / T2Mに相当しそう。合わせて考えると、相互補完ができそうですね。
スクラムだけでなく、カンバンも盛り上がってきてますね。興味を持たれた方は、ぜひ公式サイトKanban Guidesもチェックしてみてください!





