第6回 AI/人工知能 Expo【秋】参加の記録
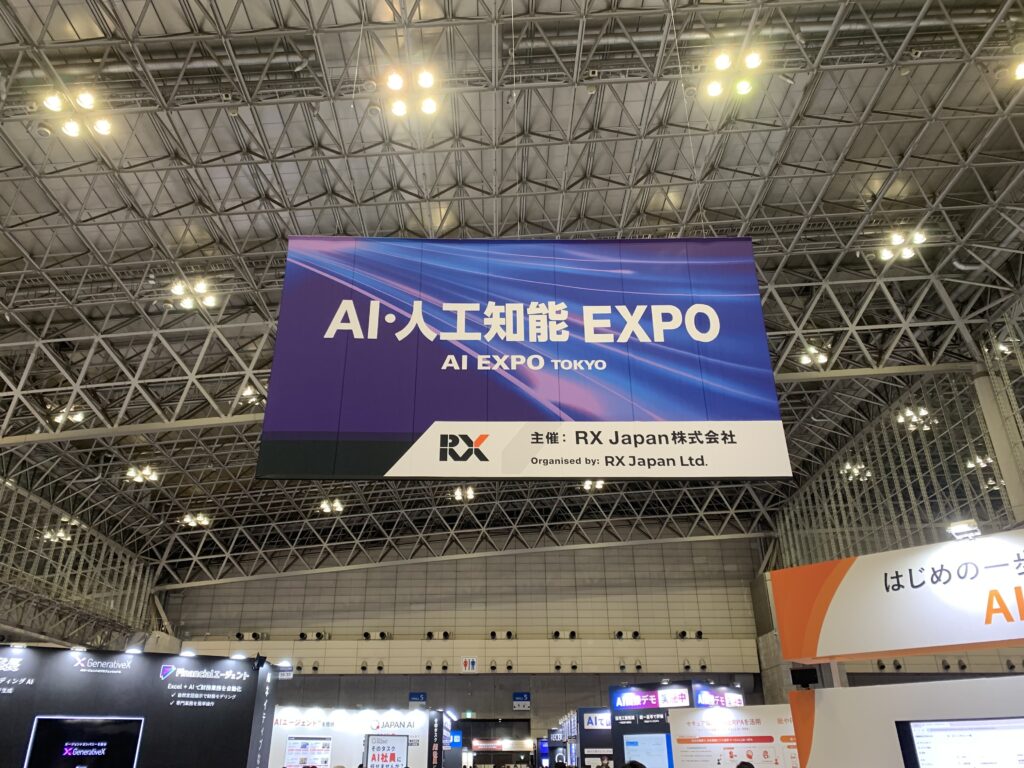
ーSaaS、AI Agent、RAGー
プロローグ
2025年10月8日(水)〜10日(金)に幕張メッセで開催された Next Tech Week 2025[秋] の一環、AI・人工知能 EXPO に参加してきました。
僕が会場に足を運んだのは、10月9日の午後です。
AIは日々の業務で活用していることもあり、「実際にどんな製品やソリューションが出てきているのか?」をこの目で見てみたい、というのが参加のきっかけでした。
最初のブースでカバンをもらい、立ち見でセッションをひとつ聞いたあと、そこからはとにかく会場をひたすら歩き回りながら──
「どんなサービスを、どういう形で提供してるんですか?」
と、ひたすら話を聞いて回るモードに突入。
チラシやパンフレットを片手に、ブースをひとつずつ見て回った中で印象に残ったこと、メモとして残しておきたいことを、今回のEXPO参加の後記として、以下にまとめてみました。
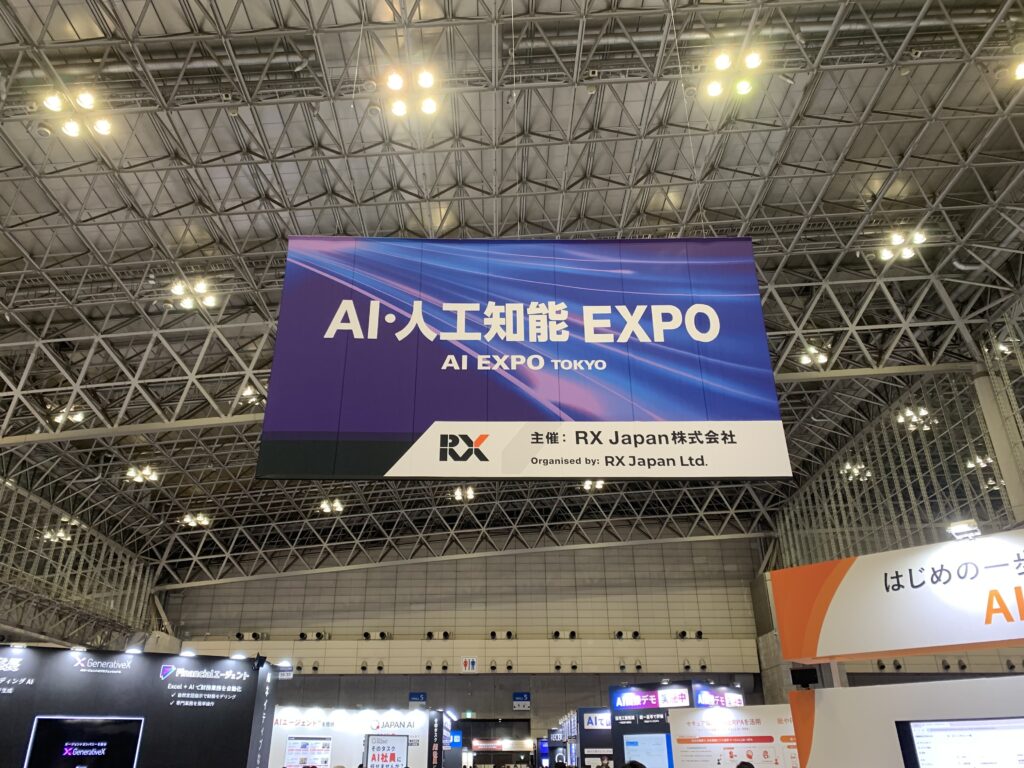
SaaS+AIエージェント系サービス
- 各種テンプレートを選択し、自ら必要な情報を登録することで利用を開始できる。
- テンプレートは約100種類もあると自慢するところも。。
- 議事録のサマリや企業内資料からQ&A対応など
SaaS+ノーコード型AIエージェント構築サービス
- ノーコードでAIエージェントを構築可能。
総合AIサービス
- 企業の業務全体を診断し、AI導入による効率化の可能性を提示する。
- コンサルティングを含み、業務改善の起点やROIなどを含めて提案を行う。
AI活用に関する教育サービス
- AIの具体的なユースケースを通じて活用方法を学習させるなど。
- AIツールの使い方に関する研修やワークショップも提供さなど。
AIに学習させるためのデータクレンジング
- データの整備・クリーニングを行い、AIが正確に学習できる状態にする。
- ノイズ除去、形式統一、欠損補完などを含む。
AI社員のようなサポートAI
- 部長や課長といった管理職の業務を支援する。
- チャートの分析・評価などを実施する機能を持つ。
RAG型を前面に出したAIサービス
小さなブースでしたが興味があっていろいろ聞いてみました。
- ユーザーの質問をベースに高品質のプロンプトを仕上げてくれる(プロンプトの生成をサポート)。
- しかも、パブリックLLMを使わないらしく、ローカルでやるとか
- それ以上は、言えない(企業秘密らしい)
- 何かのローカルLLM??、Fine Tuning??
- まるでパブリックLLMのように見えた
- しかも、パブリックLLMを使わないらしく、ローカルでやるとか
- 膨大な文書をローカルでサマリーし、プロンプトとともにLLMへ入力する仕組みがある
- 最適な内容を特定できるらしい
- この特定も、パブリックLLM使わず
- データはS3上に保存されているようだが、それ以上の詳細は企業秘密らしい
- AWSナレッジベース使うのかということも回答得られず
- データレイクのファイルを沢山おいて、瞬時に最適な内容をサマリできる?!
- 最適な内容を特定できるらしい
既存サービスにAIを部分的に追加したサービス
- 既存のBIツールなどにLLMを組み込み、チャット対応やレポート作成とかを可能にする。
エピローグ
自分にとって今回の EXPO を一言でまとめるなら、SaaS・AIエージェント・RAGの三本立て。
まさに「AIエージェント元年」と言ってもいいかもしれません。
大規模言語モデルがもたらす変革について、誰もが熱く語っていました。
私自身も業務で大いに活用しています。
それでも、ワクワクだけでなく、どこか不安が混じるのも正直なところです。
「自分の仕事には、どんな影響が出てくるのだろう?」
便利に使いながらも、心のどこかで「AIは脅威になるかもしれない」と感じている。
そんなとき、「AI社員」というチラシを配っているブースに出会いました。
思わず「もうできたんですか?」と聞いてしまいましたが、
そこにあったのは、私が思い描いていた完成形にはほど遠いものでした。
未来はもう始まっている。
でも、そこにはまだ、私たち自身の手で選び、形づくる余地がある――
そんなことを考えながら、私は会場を後にしました。





