情シスの「探せない」をどう変える?— NotebookLMで”回る知識”へ(第1回)

推定読了時間: 5分
著者: 今良太(情報システム)、紺野繁夫(AgileCoE)
導入
「ドキュメントはあるはずなのに、どこにあるか探せない」「更新したいけど、手が回らない」—情報システム部門なら、誰もが一度は感じたことがある悩みではないでしょうか。Creationlineの情シスチームでも同じ課題を抱えていました。そこで、NotebookLMを使って小さく始めてみることにしました。この記事では、その取り組みの背景と、試行錯誤しながら見えてきた戦略をご紹介します。
1. 改築を繰り返した"空中楼閣"—情シスドキュメントの現実
Creationlineの情報システム部門では、組織の成長とともにドキュメントが増え続けてきました。ただ、その実態は「改築改築改築を繰り返している」状態だと、情シスの今さんは話します。
「どこに情報があるのか、めっちゃ情報あるけどこれいつの?という状態になっちゃってる」(今さん)
オリエンテーション資料も、つい先月ようやくセミセルフ化できたばかりです。当初はeラーニング化も検討したそうですが、そこまでの工数をかける前に、まずは現状を少しでも改善したいという思いがありました。
課題の本質
- 散在する情報: 複数の場所にドキュメントが分散している
- 更新の遅れ: 管理者が不在で、古い情報がそのまま残ってしまう
- 検索の困難: 必要な情報にたどり着くまでに時間がかかってしまう
特に情シスは現在1名体制(BPサポートあり)ということもあり、「なかなか手が回らない」というのが正直なところだそうです。
既存の情シスのガイドブック(情報は一元管理されているが、ドキュメントは分散している)
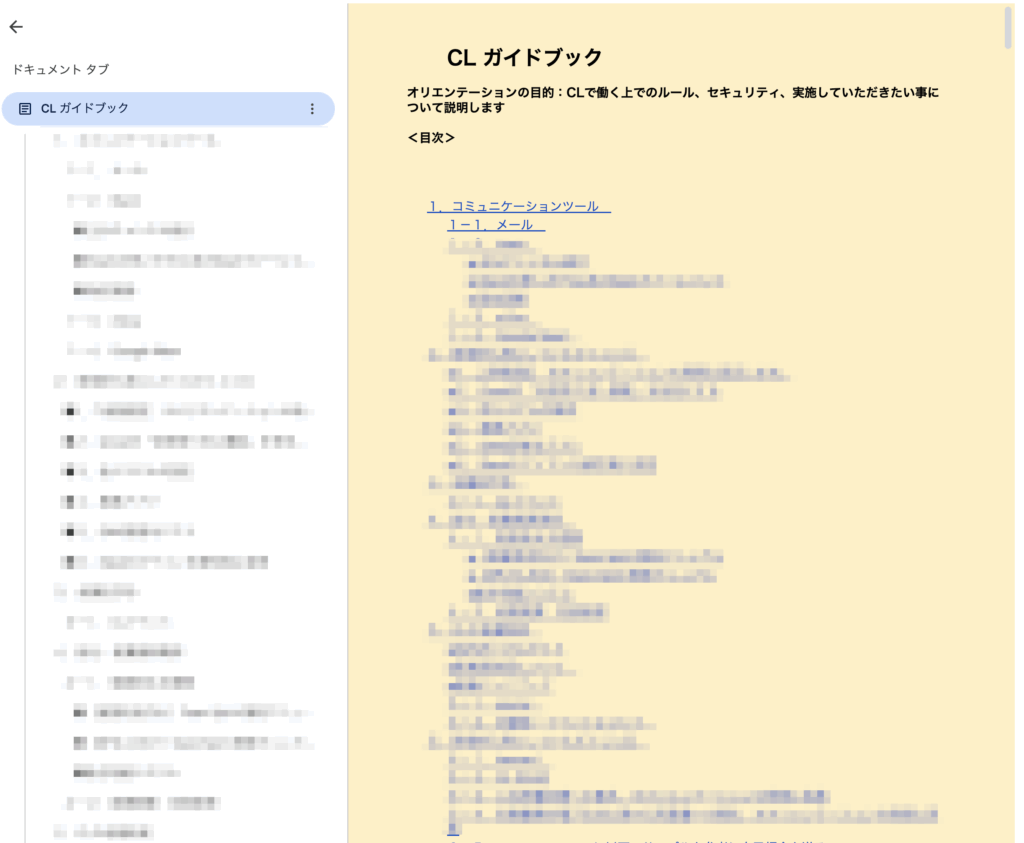
2. NotebookLMで「探す」から「聞く」へ
そこで注目したのが、Google NotebookLMです。NotebookLMの特徴は、引用元を明示しながら回答してくれる点にあります。
NotebookLMの活用メリット
1. 古い情報の特定が容易になる
「いろんな多角的な面から質問してみたりして、ここおかしい、古いみたいなのが分かると、その箇所が特定できる」(紺野)
従来は全ドキュメントを目視で確認する必要がありましたが、NotebookLMなら質問を通じて問題箇所を効率的に見つけることができます。
2. ユーザーからのフィードバックループが生まれる
NotebookLMを公開すれば、ユーザーが自分で調べ始めてくれます。その結果、「辻褄が合わない」「よくわからない」という質問が情シスに寄せられるようになります。それをチケット化して、ドキュメントを更新していく—このサイクルが回り始めれば、自然とドキュメントが最新化されていくという仕組みです。
3. 体裁からの解放
従来はドキュメントの体裁(フォーマット、見出し構造など)を整える必要がありましたが、NotebookLMではその必要がありません。
「正しい情報が保管されていれば、別にそれがMarkdownファイルだろうが、ドキュメントだろうが、関係ない」(紺野)
さらに、音声で独り言のように変更内容を喋ったものをレコーディングして投入すれば、それだけで情報がアップデートされます。手作業でドキュメントを整形する手間を大幅に減らせるのは嬉しいポイントです。
トライアル中のガイドブック(読み手の質問に合わせて回答を抽出してくれる)
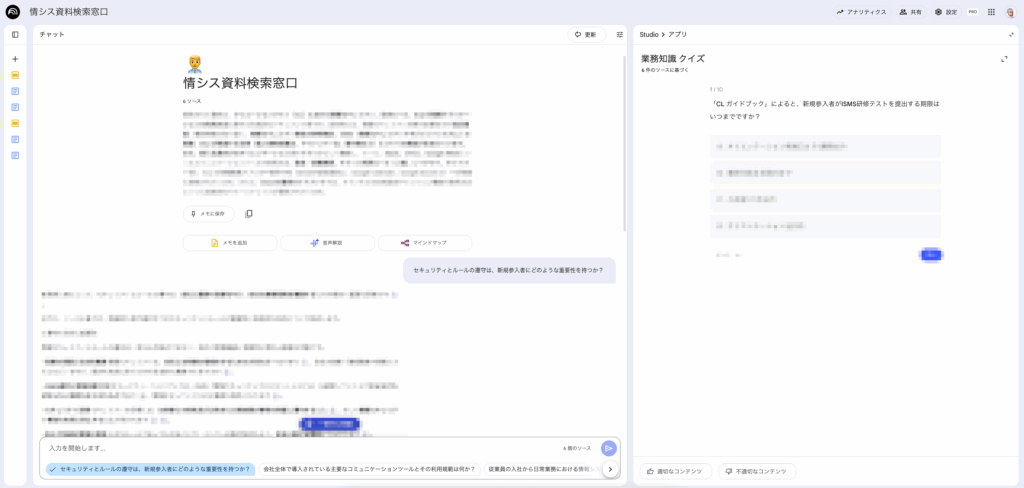
3. ベータ版で育てる—段階的導入の戦略
会議の中で、重要な気づきがありました。それは、オリエンテーションでいきなり使うのはリスクがあるという点です。
「オリエンテーションってスタートの部分じゃないですか。そこで古い情報を与えてしまうっていうのがやっぱりネック」(今さん)
そこで考えたのが、段階的に導入していくという戦略です。
導入ステップ
- 既存メンバー向けベータ版公開
- まずは業務を行っている既存メンバーに先行公開
- 「こういうことやろうとしてるんだけど」と正直に伝える
- フィードバックを情シスのSlackチャンネルやチケットで受け付ける
- 情報の最新化
- ユーザーからの質問やフィードバックをもとに、優先度をつけてドキュメントを更新
- 情シス担当者のペースで少しずつ消化していく
- 中途入社者のオリエンテーションで試験運用
- 少人数で効果を検証してみる
- 新卒オリエンテーションでの本格導入
- 大人数でも安心して使える状態になってから展開する
この段階的なアプローチなら、「古い情報を与えるリスク」を最小限に抑えながら、実用性を高めていけそうです。
4. ドキュメントの"体裁"から解放される
NotebookLMのもう一つの強みは、インプット情報のフォーマットに自由度がある点です。
多様な入力形式
- Markdownファイル
- Googleドキュメント
- 音声ファイル(文字起こし後)
- PDFやスライド
例えば、「Slackの利用規約3.0に関して、こういう点がこういう意図で更新されました」と動画で喋ったものを入れてもいいですし、そこからテキストを抜き出したものを入れても大丈夫です。
「ドキュメントの体裁にこだわらなくても、ドキュメントで出してくれる」(紺野)
これにより、情シス担当者は「情報を正しく記録すること」に集中でき、「見栄えを整えること」からは解放されます。
5. 小さく始める—2週間30分の実験
この取り組みで注目したいのは、投資がとても小さいという点です。
実験の前提条件
- 工数: 2週間で30分程度
- 撤退基準: 改善効果が出なければやめる
- ツール: Google Workspace利用企業なら無料で使えるNotebookLM
「無料でそれこそ今ほとんどの企業でGWSの環境があるので、GWSいたらこれ使えるんですよっていう流れはだいぶ導入しやすい」(今さん)
大規模な投資や長期計画ではなく、「まずやってみる」という姿勢で始められます。この軽さが、情シスのような限られたリソースで動くチームにとっては、とても大切なポイントだと感じました。
決定事項 / 未決事項 / 次アクション
✅ 決定事項
- NotebookLMを使った情シスドキュメントの検索性向上に取り組む
- 既存メンバー向けベータ版として先行公開する
- 改善効果が出なければ撤退する(スモールスタート)
- 2週間に1回、30分程度のブレストを実施
- Slackにプロジェクト専用チャンネルを作成
🔄 未決事項
- ベータ版の具体的な公開時期
- フィードバックの収集方法(Slackボット化するか等)
- 情シスポータルをNotebookLMに完全移行するかどうか
📋 次アクション
- 今さん: 情シスポータルのマニュアルをNotebookLMに投入して実験開始
- 紺野: この取り組みをブログ記事化し、社内外に発信(本記事)
- 両名: 2週間後にブレストを実施し、進捗と課題を共有
横展開の可能性
会議では、この取り組みが情シス以外にも応用できそうだという話も出ました。
他部門への展開例
- 人事部門: 社内規約や福利厚生制度をNotebookLMに投入して、チャットボット化
- プロジェクトチーム: Slackでのやり取りやドキュメントを集約して、「何だっけ?」を解消
- 営業・マーケティング: 事例集や提案資料の検索性を向上
特に人事規約のような「リアルタイムで変わらない情報」は、NotebookLMとの相性が良さそうです。
「規約って基本的にリアルタイムじゃないですか。社内規定を全部食わせればもう、そこで1つのチャットボット的なものが出来上がる」(今さん)
3行要約 & 読者アクション
📝 3行要約
- 情シスドキュメントの「探せない」「古い」問題に、NotebookLMで小さく挑戦
- ベータ版で既存メンバーに先行公開し、フィードバックで情報を最新化してからオリエンテーションへ
- 2週間30分の工数で始められる軽さと、体裁不要の柔軟性が強み
🚀 読者の次の一歩
- 社内の情シス・総務担当者: 自社の散在ドキュメントをNotebookLMに投入して実験してみる
- エンジニア: プロジェクトのドキュメントやSlackログをNotebookLMで整理してみる
- 経営・マネージャー: 小さく始めて効果を検証する文化を、自チームに取り入れる
次回予告
第2回では、実際にNotebookLMに情シスポータルのマニュアルを投入して使ってみた使用感と社内公開に向けた準備結果をご紹介する予定です。
**この記事に関するご興味・ご質問がありましたら、Creationlineコンタクトまでご連絡ください





