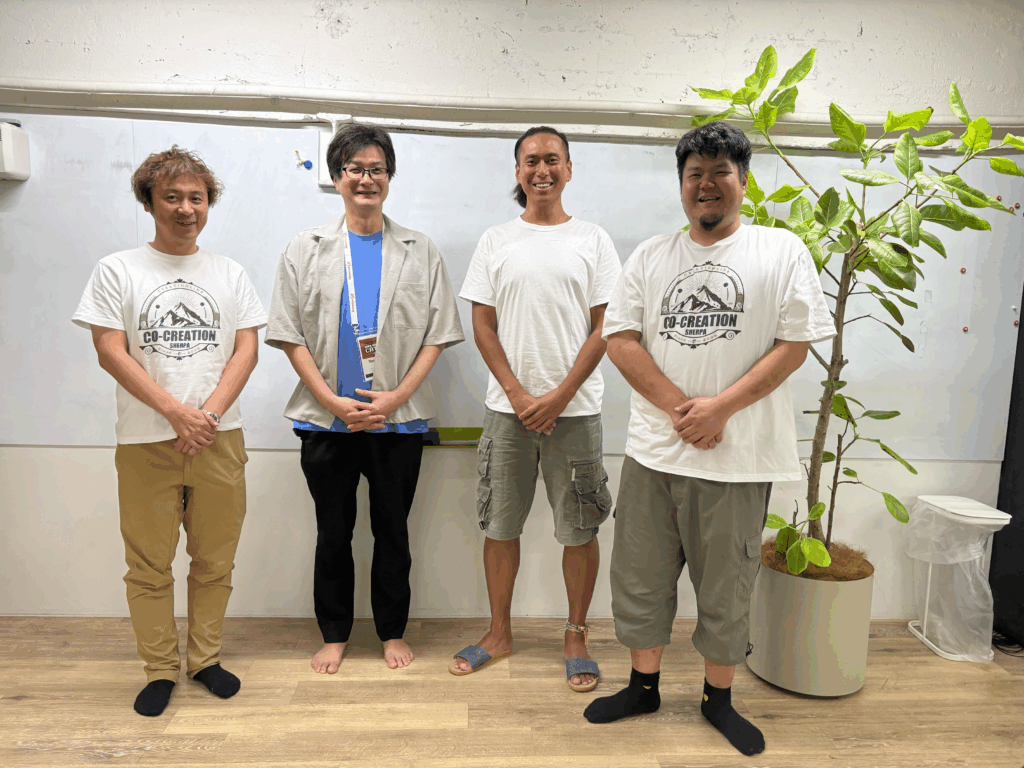生成AIの有償ライセンスを全メンバーに──生成AI活用が当たり前の未来に向けて(社員インタビュー記事)
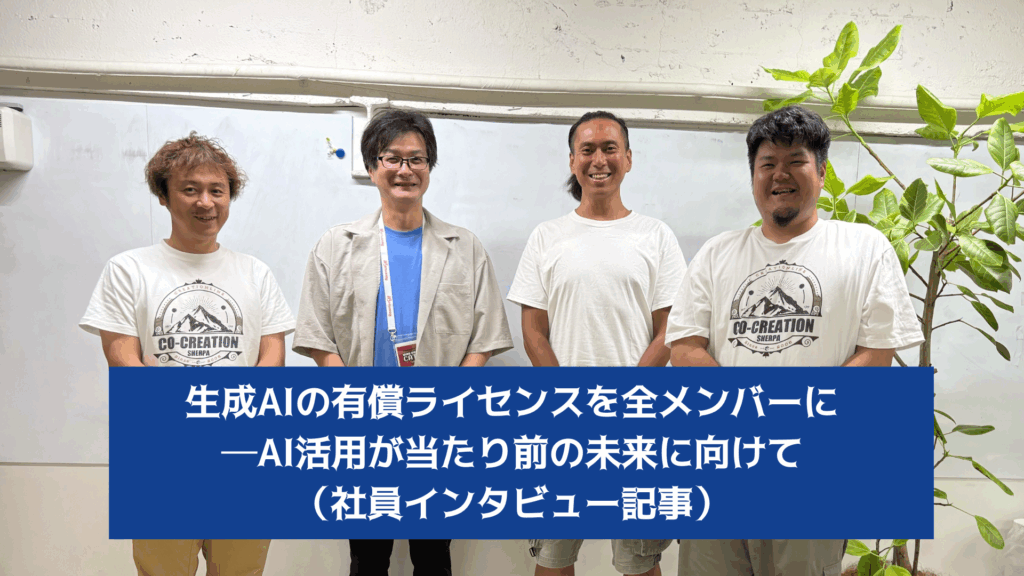
こんにちは、クリエーションラインCHROの小笠原です。
定期的に、人事施策のご紹介をしておりますが、今回は会社全体のレベルアップを推進されている「人」にフォーカスしたインタビューをブログにしました。
CLでは、生成AIが登場した初期の段階から強い関心を持ち、開発エンジニアを中心に新たなツールの導入を進めてきました。それに伴い、生成AIツール「ChatGPT」の有償ライセンスを全メンバーに提供するという挑戦的な取り組みを実施しています。これにより、私たちは希望するすべてのCLメンバーが、新進気鋭の生成AIツールをいち早く業務に活かせる環境を実現しています。
これは、単なるツールの提供にとどまらず、仕事のやり方そのものを変革するための戦略的な投資でもあります。今回は、その背景や狙い、そして今後の展望について、CTOの荒井さん、AI領域を担当するマネジャー大石さん、情報システムを担う今さんにインタビューしました。
これまでのAI活用の歩み
小笠原:まず、CLではこれまでどのようにAIに取り組んできたのでしょうか?
荒井:ChatGPTが登場したのが2022年11月。その直後から、社内向けのAI/LLM勉強会を定期的に開催してきました。これまでに8回ほど実施し、技術進化のトレンドや活用可能性について幅広く共有してきました。
その流れで、GitHub CopilotやAzure OpenAIの試験導入、CursorやBoltのハンズオンも行いました。エンジニアだけでなく、他部門のメンバーも巻き込んで取り組んできた点が特徴です。
大石:特にDiftyやBolt.newなどは、自社環境への導入検証もしました。ライセンス費用やセキュリティ面を考慮し、当初はオンプレで動かす選択をしましたが、結果的にはSaaSの方が使いやすいという学びも得られました。
ChatGPTライセンス導入の背景
小笠原:今回、全メンバーにChatGPTライセンスを提供する判断に至った背景を教えてください。
荒井:以前から希望者には個別にライセンスを付与していたのですが、ChatGPTの機能が急速に高度化してきたこと、そしてそれに合わせて業務フロー全体の見直しが求められるようになったことが大きな要因でした。
「使える人が使えばいい」ではなく、会社全体としてAI活用のレベルを底上げする必要があると判断しました。
大石:バックオフィスなど非エンジニアのメンバーも、AIを前提にした業務スタイルへと確実に移行してきている実感がありました。その流れを受けて、「全員で使っていく」方向にシフトしました。
今:情報システムの立場としても、誰もがスムーズにAIを使えるようにする環境整備は必須だと考えています。ハードルを下げ、日常の一部として使ってもらえるようにするのが目標です。

実際の効果と変化
小笠原:ライセンス配布後、社内にどんな変化が見られましたか?
今:2025年7月末時点で、全社員の約90%にあたる80名以上がChatGPTライセンスを申請しました。申請していないメンバーも、Geminiなど他の生成AIを使っており、全社的に「誰もが何かしらAIを使っている」状態になっています。
大石:非エンジニア層でも、業務マニュアルの作成、請求金額の自動算出、企業調査や報告書作成など、実務的なタスクの効率化が進んでいます。
大石:Slackアプリ「玄米茶」という自社開発のAIエージェントを使って、情シスへの問い合わせ対応やGoogle Cloud環境の構築も自動化し始めています。たとえばこのCL Tech BlogについてもAIの力で投稿をしやすくしております。具体的には、「ブログを記事化して」と指示するだけで、テンプレートとメモを元に記事の下書きまでAIが生成できるようになりました。社内情報発信のスピードが圧倒的に上がっています。
大石:誰もが自律的に働けるようにするには、ツールの民主化が不可欠。生成AIの全社展開は、私たちの経営理念「HRT+Joy」の体現でもあると感じています。
今後の展望
小笠原:これから、生成AIをどう活用していく構想ですか?
荒井:生成AIは、もう特別な技術ではありません。今後はClaude CodeやCode Interpreterなどより高機能なツールの導入も視野に入れつつ、AI CoEを中心に全社的なスキル向上を進めたいと考えています。
大石:「これAIでできるかも?」と思ったら、とにかく触ってみること。その小さな実験の積み重ねが、大きな改善につながる。AIは今や、業務の前提条件になりつつあります。
荒井:AIが担える領域が年々拡大していくでしょう。2025年の今はまだ人が多くの業務を担っていますが、2030年には、人はより価値創造的な領域に集中し、反復的・定型的な業務はAIに任せるようになるでしょう。社内のナレッジ検索、業務処理、外部との連携などもAIが仲介し、人は監督・判断・補完の役割を担います。企業活動の中心が、徐々にAI Agentへとシフトしていく未来になると考えています。
こうした未来像を、単なる構想で終わらせず、日々の仕事の中で少しずつ実現していけるって、本当に面白いしワクワクしますよね。
生成AIは、あくまで“道具”です。けれどその使い方次第で、私たちの仕事も、チームの在り方も、大きく変わっていきます。
クリエーションラインは常に新しいチャレンジを、今後も続けていきます。