SalesZine Day 2025 Summer参加レポート:「顧客起点」の思考と「データに基づいた客観的な行動・判断」の重要性を学ぶ

こんにちは。今回のBizOps奮闘記では、2025年7月24日(木)にコモレ四谷タワーコンファレンスで開催された「SalesZine Day 2025 Summer 新時代の『営業インフラ』と顧客起点の変革への挑戦」の参加レポートをお届けします。年2回定期的に開催されているこちらのイベントは、会場の規模や参加者数が内容的にちょうどよく、落ち着いてセッションを聴講できました。
少し長いのですが、最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。
参加動機と参加セッション
SFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)の導入、そして組織におけるデータ活用の課題と取り組みについて、参考になる情報を得ることを期待して参加しました。合計14ある講演の中から、以下の4つのセッションを聴講しました。
- 日立ソリューションズが語る!営業現場を変革するCRM/SFA活用術
- “成長を楽しむ営業が、会社を変える。”-営業育成策のモデル化と展開に挑む CTCのセールスイネーブルメント-
- 「とりあえず入力」から「行動・売上が変わる」へ。営業組織が動き出すSFA活用の裏側、全部見せます!
- その分業、逆効果かも? THE MODELの次世代を担う顧客起点アプローチ「カスタマーモデル」とは
イベントレポート
日立ソリューションズが語る!営業現場を変革するCRM/SFA活用術
このセッションでは、大手のCRM/SFA活用事例から学びを得ることを目的として参加しました。ユーソナーの鈴木彩乃さんがモデレーターを務め、日立ソリューションズの石原あゆみさんが回答する対談形式の講演でした。
日立ソリューションズは、営業業務の属人化、組織の実力不明瞭化、そしてパイプライン管理の実現を目指してSFAを導入したものの、入力課題により十分に活用できなかったという経緯がありました。また、顧客の購買行動の変化に対応するため、御用聞きから提案型営業への変革が必要だと感じていたそうです。
「現在地を知らないと戦えない」という考えのもと、Plan(戦略立案)、Do(戦略実行)、Check(状況確認)、Action/Analyze(分析/改善)のPDCAサイクルを回していました。
• Plan:新規プラン立案時に、企業マスタと自社の商品マスタ・納品実績をマッピングしたヒートマップを作成し、どの領域で商品が購入されているか、いないかを視覚的に確認できるようにしました。
• Do:SFAは活用できているものの、活動履歴データの拡充が課題であり、会議録音をテキスト化して案件情報として記録する取り組みを進めているとのことです。将来的には、情報が蓄積できたら営業活動を「型」にして活用したいと考えているそうですが、これはまだ途上にあると述べられていました。
• Check:業績認識用のボードをTableauで作成し、所産額とSFA案件総額を比較し、充足情報を監視しています。
• Action/Analyze:組織軸で複数年にわたる成長を可視化し、顧客の成長率に合わせて自社の提供サービスも成長させられているかという視点で分析を行っていました。
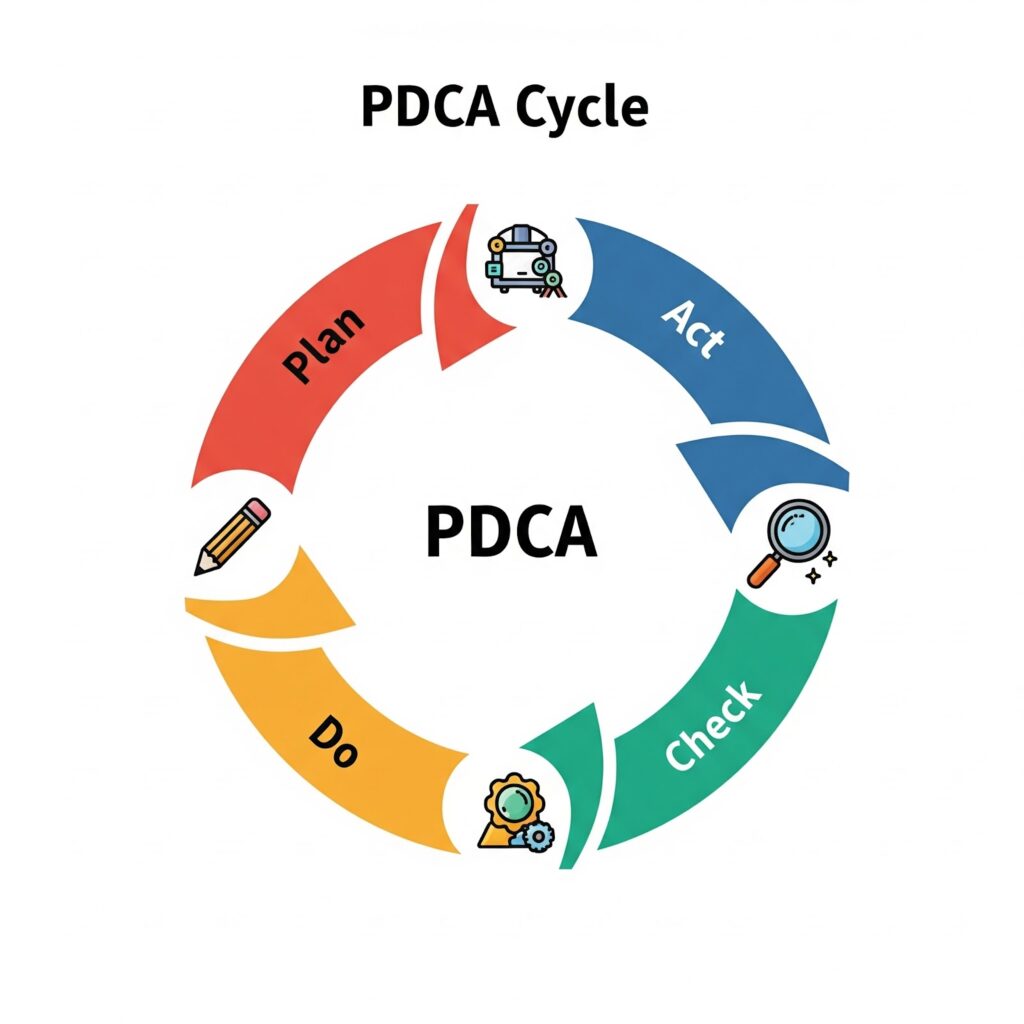
感覚ではなくデータに基づいて行動し、客観的な判断とメンバーとの合意形成にデータで根拠を示す
AIを営業員の支援ツールとして活用していく考えもあり、特に商材が多いため、CopilotやAlliLLMのチャットボットを活用し、状況に応じた提案アドバイスを得たいと考えているそうです。一方で、管理系業務の進捗が課題であり、業務部門が本来の業務に集中できる環境を目指しているとのことでした。
CLと日立ソリューションズでは企業規模が異なるので単純な比較はできませんが、CRMへの「情報入力」が課題となっている点は共通していました。どのタイミングなら入力しやすく、入力を習慣化するためにはどのような工夫ができるか日々悩んでいるところなので、参考になるアイデアが得られたセッションでした。
“成長を楽しむ営業が、会社を変える。”-営業育成策のモデル化と展開に挑む CTCのセールスイネーブルメント-
今回のイベントで最も期待していたセッションです。CTCのCROグループ営業戦略本部全社営業企画部の五十嵐淳さんによる講演でした。
多くの企業が抱える「属人化・データ散在・OJT頼みの人材育成」といった共通課題に対し、CTCが取り組んだ内容が紹介されました。業績が絶好調の中で、トップダウンで改革に取り組んでいた点には非常に感銘を受けました。体力があるうちに改善を図るという心構えが、安定した業績に繋がっていると納得できます。
湊原孝徳CROが掲げた中期ビジョンは、これまで営業が担っていた「ブランディング、マーケティング、セリング、カスタマーサクセス」のうち、CROグループが6つの施策で支援し、営業は「セリング」に注力するというものでした。
具体的には、業務最適化、情報活用、人材育成の3つの課題を吸い上げ、構造化し、体系立てて施策を実施していきました。営業活動に必要な情報を集約したイントラサイトと、バラバラだった営業ナレッジを集約したナレッジマネジメントサイトを構築し、利用率やメッセージから迅速な改善を進め、業務最適化と情報活用の基盤を整えたそうです。
特に印象に残ったのは人材育成の話でした。現代の「物売りから事売り」へのトレンド変化に対応するため、顧客の問題を営業がより深く考えられるように、「売り手」から「買い手」の思考へと変えるトレーニングを繰り返し実施していました。SFAの「次のアクション」に必要なことを明確に記述させ、全社的な営業の共通言語づくりにも力を入れているそうです。
さらに、以下の重要ポイントを分析し、仮想顧客に対する提案や課題の構造化を通じた営業パーソンの育成を実施しています。
- 最新技術活用
- 仮説構築
- 課題構造化
- データ活用
- 効果算出

営業育成は、個々の成長目標に向けた行動実践、思考整理、専門教育の3ステップでモデル化されていました。トレーニングに加え、実践経験を持つ社内外のコーチによるコーチング、そして「共育」を実現するための共育型オンラインコミュニティでの「一言日記」共有と事務局からの問いかけにより、自己変容を促す仕組みが印象的でした。これらを6ヶ月間行い、自己変容を発表するそうです。加えて、マネジメント層の行動特性も可視化し、「人材育成成功の6割は上司次第」という考えのもと、上司が何をすべきかまでカバーする仕組みに取り組んでいました。まとめのスライドにあった「人・組織が動いてなんぼ」という言葉が、このセッションの具体的なアイデアの多さと勢いを象徴していると感じました。
こちらのセッションは当日の資料を提供していただいたので、さっそく営業部門のリーダーに共有しました。
「とりあえず入力」から「行動・売上が変わる」へ。営業組織が動き出すSFA活用の裏側、全部見せます!
Sales Goの石井賢さんによるセッションです。石井さんはあらゆるCRMを触った経験から、エクセルの見た目や使い勝手を好む日本人向けに、Salesforceとkintoneとエクセルを組み合わせた独自のSFAを開発したそうです。
石井さんの話によると、日本企業のSFA導入率はわずか10%とのことですが、このセッションの参加者は6~7割がCRM導入済みだったようで、関心の高さが伺えました。
セッションでは、エクセルでの営業管理の落とし穴や、CRMを導入しても入力が課題となる企業が多いことが語られました。入力の心理的ハードルを下げるために、「ヒアリングシートを型化」したり、フリー入力ではなく「プルダウンメニュー化」するといった具体的なアイデアが紹介されました。
SFA活用の重要なポイントとして、以下が挙げられていました。
- 共通言語で測定・評価ができているか
- 異常値を可視化し潰せているか
また、お客様を主語にしたフェーズを定義し、フェーズを上げる条件を明確にした上で確度を定義すること、前進した商談は後退しない定義にすることもポイントとして挙げられていました。
このセッションは、CRM導入初期や検討中の企業向けの内容が中心でしたが、ヒアリングシートの型化や入力項目のプルダウンメニュー化といったアイデアは、すぐにでも取り入れられる点で非常に参考になりました。ヒアリングシートの型化にはHubSpotのプレイブック機能が活用できるのではないかと思いました。
その分業、逆効果かも? THE MODELの次世代を担う顧客起点アプローチ「カスタマーモデル」とは
株式会社イノーバCEOの宗像淳さんによるセッションで、「顧客の検討行動・心理文脈・意識内力学に沿って、営業・マーケティング・CSを再設計するアプローチ」について語られました。
このセッションは、「The Model」を読んでいることを前提とした内容で、この本に影響を受けてインサイドセールスを導入したものの伸び悩んだ企業が一定数あるという事実に驚きました。
「The Model」の分業スタイルの次に提唱されたのが「カスタマーモデル」です。これは「顧客の検討行動・心理文脈・意識内力学に沿って、営業・マーケティング・カスタマーサクセスを再設計するアプローチ」と定義されています。
顧客のリアルな意思決定プロセスに沿って、部門横断で伴走するマーケティング・営業設計モデルを実現するために、どのように情報を集め、社内で調整していくかが重要とのことです。「関係構築→価値提供→示唆出し」の3ステップをいかに回していくかが鍵となります。
イノーバでは、マーケティング部門がお客様に送付するメルマガの内容を、自社サービスやニュースから顧客の参考になる情報、顧客の課題や業界の旬のテーマなど、読者に役立つ情報にシフトしたそうです。この施策を開始して3~6ヶ月で顧客の反応が変わり、インサイドセールスが電話をかけると「あのメルマガの会社ね」「楽しみにしている」といった声を聞くようになったとのこと。これは「楽しみにしてもらえる」=関係構築と言えるでしょう。なんと、メルマガの読了率が7割まで向上したそうです。
このような施策には、お客様が誰で、どのような接触をすると興味を持ってもらえるのか、接点や体験の見直しが必要です。そのためには、自社のお客様の解像度を高める必要があります。お客様の良き相談相手になるというメッセージをどう伝えるか。このセッションでは、顧客の購買検討や課題を深く把握するためには何をすべきか、顧客の良き相談相手になるための会話、感情、関係が軸となる時代において、CRMやAIといった技術を活用した営業・マーケティング活動のあり方、そしてそれらを支えるビジネスオペレーションについて深く考えさせられました。

学び・気づき:「顧客起点」の思考と「データに基づいた客観的な行動・判断」の重要性
今回のイベントで得られた最大の学びは、どのセッションも**「顧客起点」の思考と「データに基づいた客観的な行動・判断」の重要性**を強調していたことです。特に、CRM/SFAの導入・活用においては、単なる入力ツールではなく、顧客との関係構築や営業活動の質向上に繋がる「インフラ」として捉える視点が不可欠だと感じました。
- CRMの入力負荷軽減とデータ活用の促進
- 営業活動の「型」化と人材育成の強化
- 顧客の購買行動・心理に寄り添った「顧客起点」のアプローチの推進
- データに基づいた客観的な判断と、AIを含む最新技術の営業支援への活用
上記を念頭に、CLのビジネスオペレーションとしてどのような活動ができるのか、改めて考えていきたいと思いました。日ごろはモニターのデータを前にしかめっ面をしていることが多い筆者ですが、たまにはこのようなイベントに参加して、知見を広めていきたいと思います。





